the-icons-the-chelsea-boot
THE CHELSEA BOOT
若い頃からチェルシーブーツを愛用しているというメンズファッションライター、ニック・カーヴェル。ビューティーライター、ブランドコンサルタント、講演家とマルチに活躍する彼が定番シューズとして愛され続けているチェルシーブーツの魅力を語った。
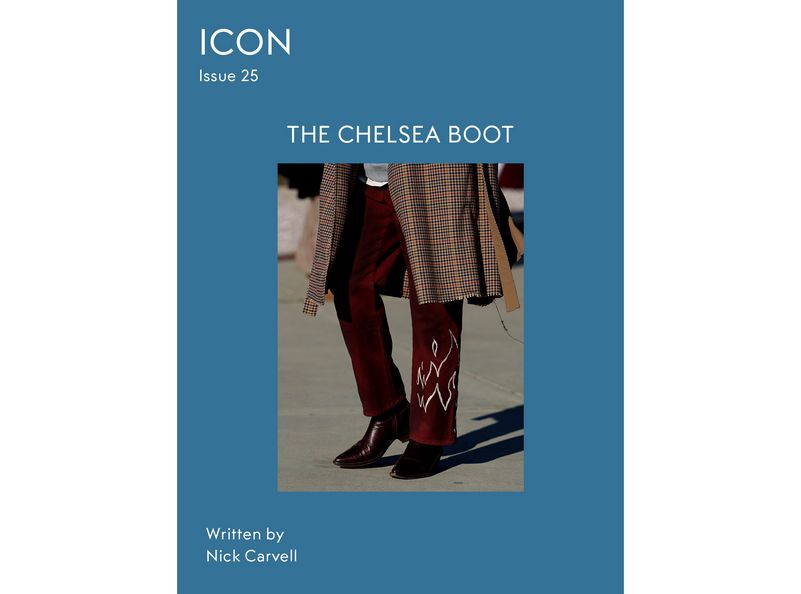

最近、私はある企業との仕事のためにロンドンのチェルシー地区に頻繁に通っている。オフィスは出入りするのにセキュリティーカードが必要な大企業然とした高層ビルで、淡いブルーのカッターシャツに紺のジャケット姿の記者が大きなコンピューターに向かって仕事をしているデスクの島を通り過ぎる度に、ここは出版社ではなく、証券取引所ではないかという気分にさせられるような場所だ。長年メンズファッション関連の仕事をしてきたが、仕事仲間はジーンズやセーターといったカジュアルウェアで働いていて、スーツなどひとりもいなかった。だからこの仕事においては自分のカジュアルなスタイルをオフィスのお固い空気感に少々馴染ませる必要があった。そう、チェルシーブーツの出番だ。
チェルシーブーツが魅力的な理由は英国の歴史にあるだろう。一説にはヴィクトリア女王お抱えの靴職人、ジョセフ・スパークス・ホールが女王の毎日の散歩のために開発したといわれている。女王と取り巻きたちは側面に伸縮性があり、ゴム仕様の靴底のブーツをすぐさま気に入った。当初は発明者の名を冠した「J.スパークス・ホール印のエラスティック アンクルブーツ」というまったくキャッチーではない名称だったが、その後、スルっと履けるスタイルから「パドックブーツ」と呼ばれるように。19世紀後半には散歩だけではなく乗馬にも活用され、その人気はどんどん拡大したという。
第一次世界大戦後、その人気は翳りを見せるが、1961年、再び陽の目を浴びることとなった。そのきっかけは時代の寵児、ビートルズだ。ジョン・レノンとポール・マッカートニーがロンドンで舞台用靴ブランド「アネッロ&ダヴィデ」の店頭に飾られていたチェルシーブーツに目をつけ、メンバー全員分をオーダーしたのだ。ただし、トゥをもう少し尖らせ、ヒールを高くする、というデザインオーダー付きだ。スリムなデニムにこのブーツを合わせたルックは結成当初のビートルズにとって欠かせないスタイルとなる。また、当時同じく絶大な人気を誇った英国のバンド、ローリング・ストーンズやザ・フーはもちろん、英国人デザイナーのマリー・クワントもチェルシーブーツを積極的に取り入れた。ロンドンのキングスロードを中心に巻き起こったスウィンギング・シックスティーズと呼ばれるユースカルチャーブームの象徴として、彼らは流行の火付け役となる。そして彼らが好んで履いていたこのブーツは、チェルシーブーツの名で広く知られるようになった。それ以来、その人気は衰えることなく、カニエ・ウエストやハリー・スタイルズ、デヴィッド・ヴェッカムからジャスティン・セローまで、現代も数々のビッグネームに愛されている。

つまり、現在のチェルシーブーツの人気はロックンロールのスターやカルチャーの流れを変えたキーパーソンたちによって作られたといっても過言ではないのだ。そしてそのロックなアティテュードは、今もしっかりと残っている。スーツの着こなしがちょっと堅苦しいなと感じたら、黒いチェルシーブーツを履いてみることをおすすめする。そうすれば、ちょっとしたアヴァンギャルド精神が湧いてきて、モンクストラップやレースアップシューズといったトラディショナルな靴を履いた大人たちに囲まれていても、俄然やる気になるはずだ。フォーマルなシーンでも通用するスマートなビジュアルなのに、どこか抜け感があってカジュアルなムードを漂わせてくれる。これこそが、このブーツ独特の魅力なのだ。気難しく、オーソドックスなスタイルを好んだヴィクトリア王朝において人気を博した理由も、おそらくそこにあるのだろう。
使い勝手が良いだけに、さまざまなデザイナーの手によって数々のスピンアウトも生まれてきた。例えばLAを拠点とする「アミリ」、パリの「サンドロ」、英国のテーラー「ダンヒル」はレザーやスエードを用いて、バンド好きが好む流線形かつ尖ったトゥスタイルを追求している。その一方で、もっとアウトドアな感性を取り入れたものもある。バイカーズジャケットで知られる「ベルスタッフ」の頑丈でヒールの低いスタイル、「トッズ」が提案するウェリントンブーツとチェルシーブーツのハイブリッドバージョン、「オフィシン ジェネラル」を手掛けるフランスのデザイナー、ピエール・マヘオがデザインしたタウンユースに適したジップアップモデルがその好例だ。
いずれにしても、犬を散歩させる時もスーツでロンドンのオフィスに出勤する時も、私が自分らしくいるためにチェルシーブーツは欠かせない存在なのだ。チェルシー地区そのものは60年代のようなトレンドスポットではなくなり、今では企業の集まるオフィス街に変貌しつつある。しかし、履く人に少しの反骨精神を抱かせるチェルシーブーツのポテンシャルは今も失われてはいない。自宅でリモートワークを済ませた後、オーバーサイズのコートを羽織ってベッドフォードのカフェに向かっている最中でも、チェルシーブーツを履くと私にアヴァンギャルドな気分を味合わせてくれる――、チェルシーブーツにはそんな魅力があふれているのだ。
Translation: Tatsuya Miura



