the-icons-the-turtleneck
THE TURTLENECK
英国版『VOGUE』をはじめ『ファイナンシャルタイムズ』が発行する『How To Spend It』、『Observer Magazine』などでコントリビューティングエディターとして活躍するケイト・フィニガン。彼女が語る、タートルネックの魅力とは?
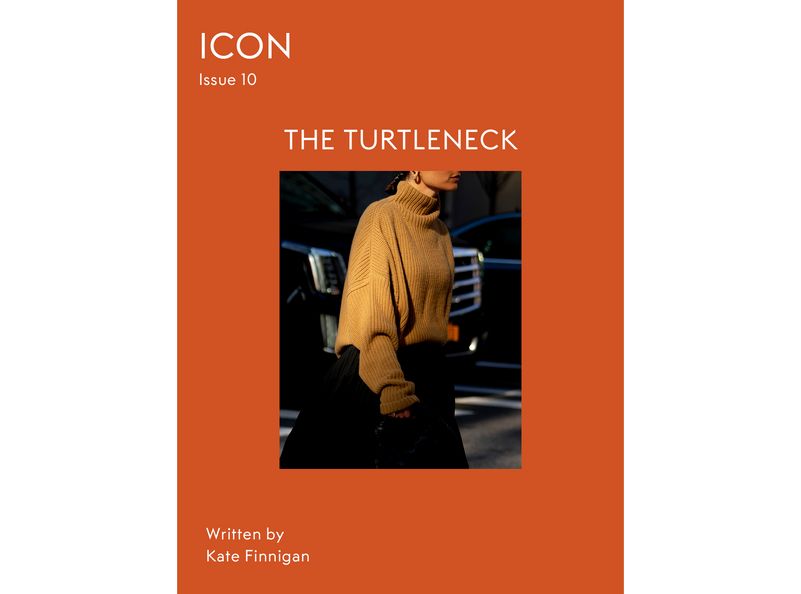

私がタートルネックを好きなのは70年代生まれだからかもしれない。とはいえ、正直言うと子供の頃は大嫌いだった。
あの頃のワードローブに並んでいたのは、チクチクするニットやキラキラのタイトシルエットのタートルネック。特にタイトシルエットのは母が無理やりに着せるものだから、首は締めつけられるし髪は静電気でめちゃくちゃで散々な思い出だけが残っている。
状況が一転したのはティーネイジャーの頃、80年代半ばだ。50年代的なアメリカンスタイル(前髪をちょろっとに垂らしたリーゼントヘアと憂いを帯びたまなざし、輪郭のはっきりした顎の男の子)が再びブームで、私もチャンキーなタートルネックのフィッシャーマンズセーターを着たジェームス ディーンのポスターを部屋に貼っていたものだ。当時の私は黒い上質なタートルネックのニットにチノパンやロールアップデニム、Dr.マーチンのブーツが定番スタイルだった。
ちなみに私はイギリス人なのでタートルネックは「ポロネック」または「ロールネック」と呼んでいた。「タートルネック」は確かにわかりやすいけどクールではない。ジェームス・ディーンはどう見たって「タートル=亀」には見えないから!オーストラリアでは「スキヴィ(下着の俗語)」と呼んでいたらしいけど、これはタートルネックよりもひどい…。
それはさておき、ハイネックの歴史は古く、なんと500年も前から着られていたらしい。当時の騎士たちは鎖の鎧の下に着ていたのだとか。ある意味とてもシックなレイヤードコーデだし、今なら逆にアリかもしれない。その後、19世紀にポロの選手が着るようになってからは「ポロネック」と呼ばれるようになった。

20世紀にはタートルネックはインテリやアート界隈の人が好んで着るようになり、1920年代にはイギリス人作家ノエル・カワードが、1950年代にはフランスの哲学者ミッシェル・フーコーが着用。1957年にはオードリー・ヘップバーンが映画『パリの恋人』で黒のポロネックを着て、共産主義かぶれの書店員ジョー・ストックマンを演じて話題に。「ハイネックのプルオーバーには『私はみんなとは違う』という主張がひと目で伝わる、パワフルな魅力が宿っている」という彼女の台詞がハイネックの人気を決定づけた気もする。
幼い頃は嫌悪感さえ抱いていたタートルネックが、今では冬の定番としてクローゼットに並んでいる。なぜなら、それは知的で自由なイメージがあって世界中で愛されているし、モダンでシャツやTシャツよりもスタイリッシュだから。コレクションのために出張する時は必ずネイビーのカシミアのポロネックのニットを入れるほどだ。
基本的には着回しやすくてワンピースやセーターの下にも重ねられるような、細身で薄手のニットのタートルネックが好きだ。ハイウエストのボトムスにタックインして、ニーハイブーツに合わせるもの素敵だと思う。たとえばロクサンダのタートルネックをスリップドレスやエプロンドレスとあわせれば北欧風のキュートなルックが出来上がる。デンマークのデザイナー、マーク タンのオートミールのような質感のタートルネックセーターは首元から袖にかけてアシンメトリーな縫い目がアクセントになっていて、外出自粛が始まる前はよく着ていたものだ。ハイウエストのマキシ丈スカートやアクネのチノパンにブーツを合わせることが多かった気がする。
バストのサイズにかかわらず、ポロネックはボディラインをやさしく引き立て、個性を輝かせてくれる。胸が大きい人には似合わないという人がいるかもしれないけれど、それは体型差別というもの。裾をタックインして、流れるようなボディラインを際立たせるファッションをみんなに楽しんで欲しい。
そういえばヴィクトリア ベッカムのようなスリーブパッチが付いたフィッシャーマンスタイルのポロネックはポートレートにもよく使用されている。トム・クルーズやレオナルド・ディカプリオ、フィービー・ファイロ……、みんな顔を引き立ててくれるチャンキーなポロネックを着て写真に収まっている。髪をネック部分に入れたままにするフィービーのスタイルはノンシャランな雰囲気も演出できるのでおすすめだ。
着回しができて「私はみんなとは違う」というメッセージを発信できるタートルネックは、あなた自身の個性とスタイルを代弁してくれる心強い味方だということを、ぜひ覚えておいてほしい。



